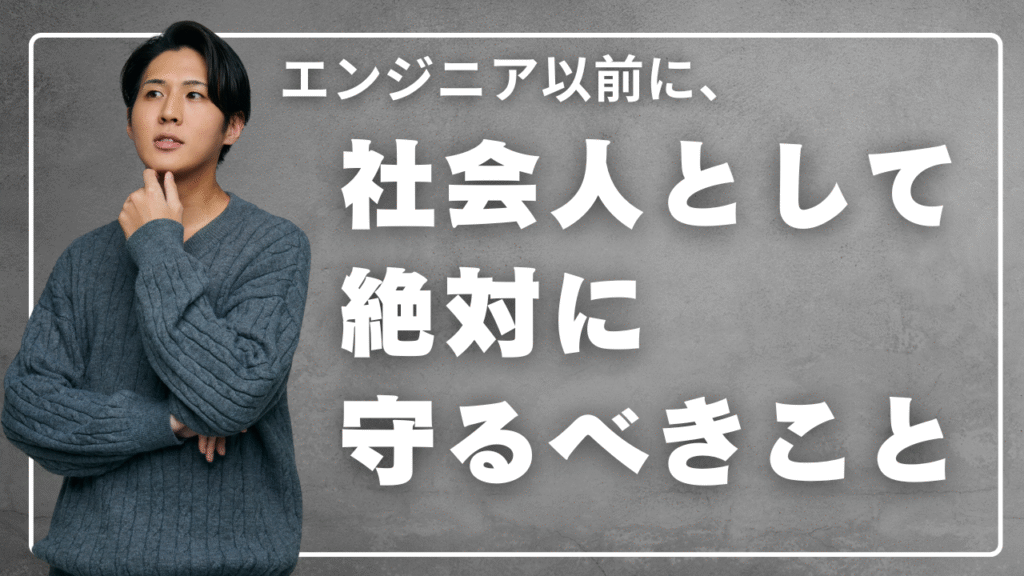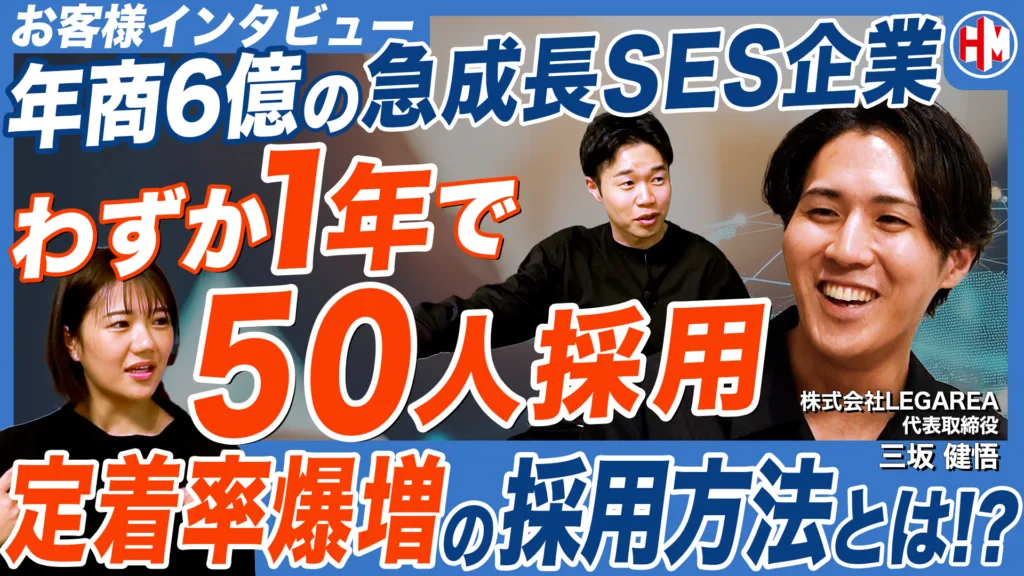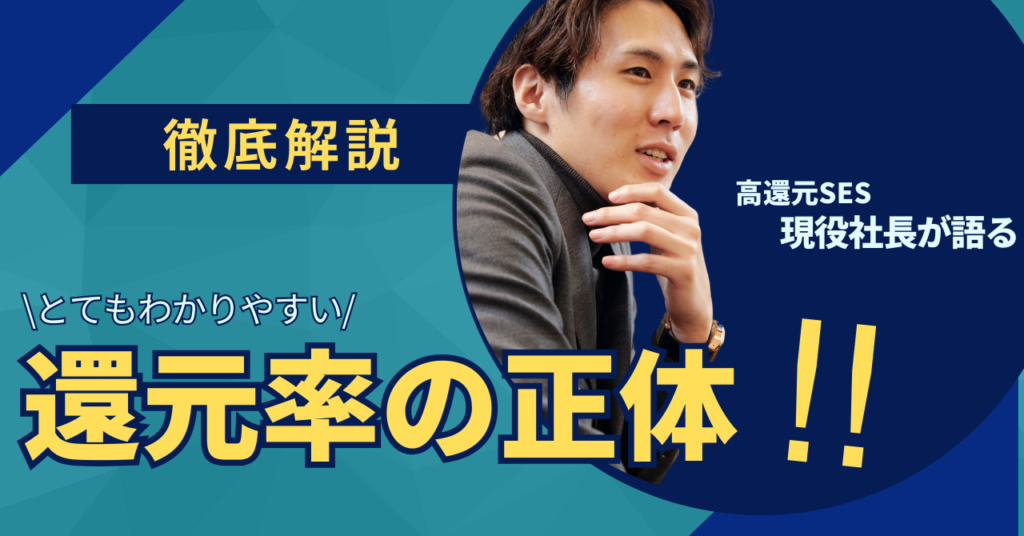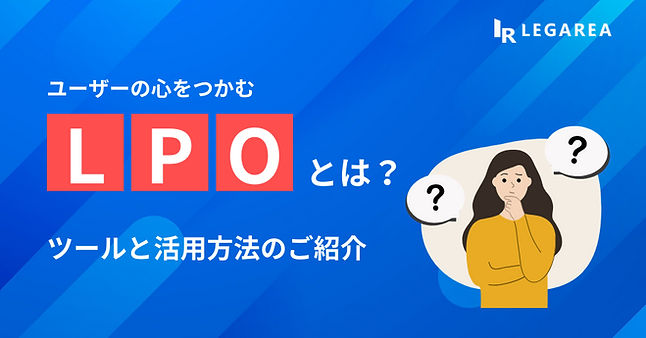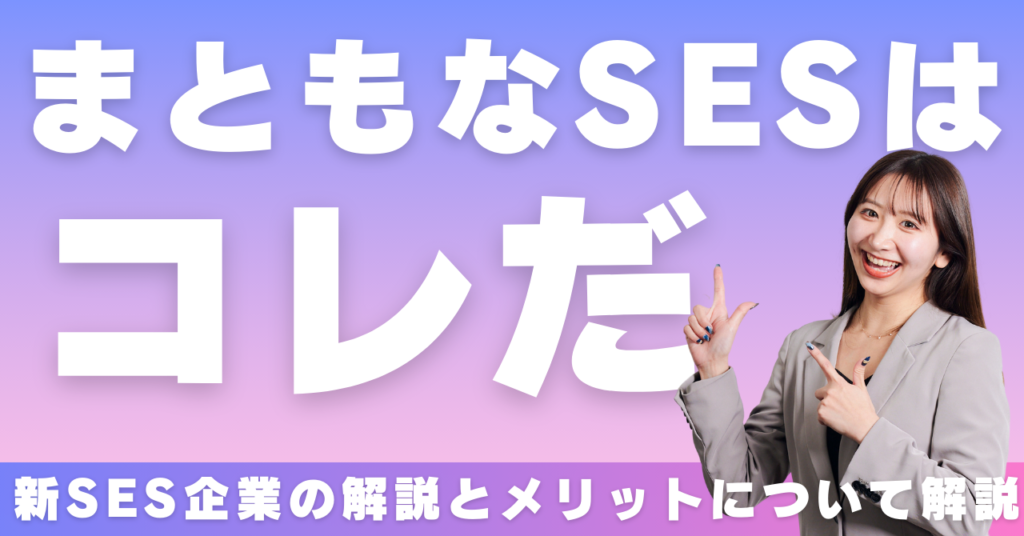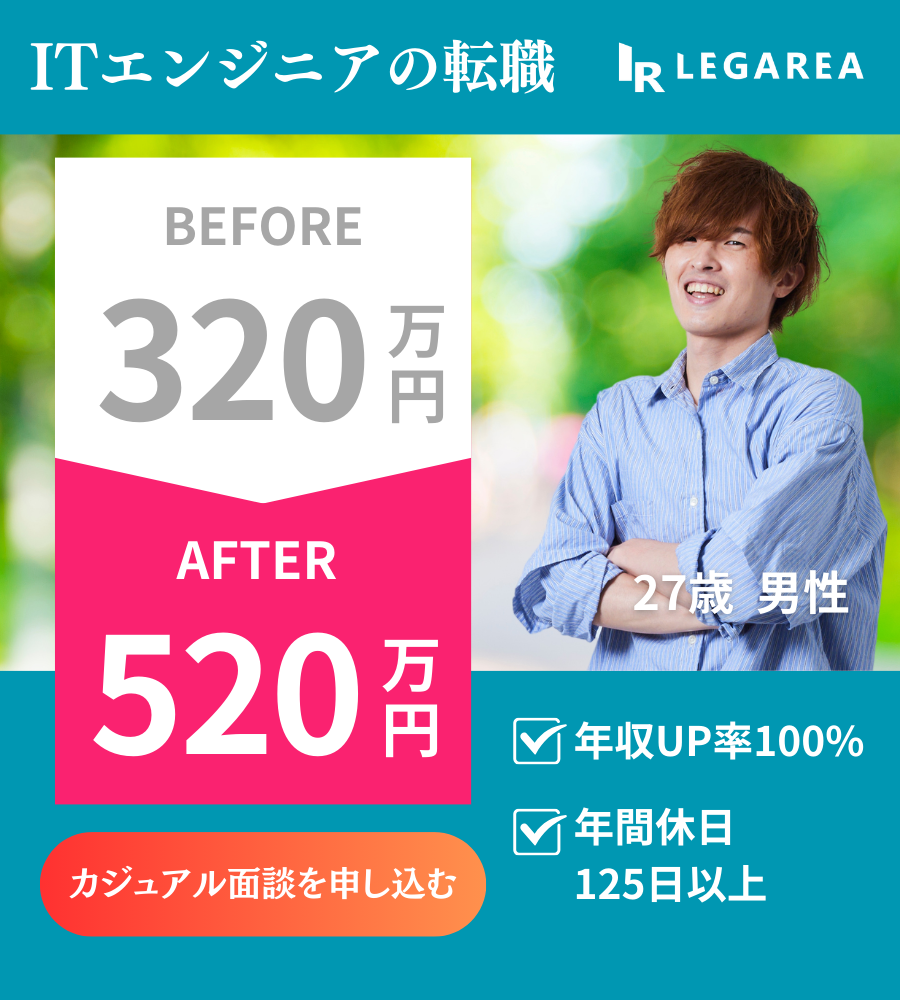スキルはいらない。対応力を磨け

こんにちは!代表の三坂です。
すっかり暖かくなり花粉の季節の到来。うっとうしいです。
アレグラを飲んでいますが何年も飲み続けていると効果は薄れてきます。そこで最近は顔にスプレーをして対策をするタイプを選んでいます。イハダ?かなんかでしたが、効果テキメンです。めちゃくちゃおすすめなので花粉ひどい方はぜひ試してみてください。

さて、本日はエンジニアのみなさんにぜひ投げかけたいテーマです。スキルを追い求めるのは正しい努力か?というテーマです。あくまでSES業界における話です。
結論私は、テクニカルなスキルよりも、「対応力」「立ち振る舞い」「調査力」を鍛えるべきだと思っています。
具体的な詳細について執筆していきます。
スキルを磨くよりも、現場での立ち振る舞いや調査力を鍛えるべき理由
エンジニアの成長において、最も大事なものは何か?
「技術力」と答える人も多いでしょう。たしかに、エンジニアとしてのスキルを磨くことは重要です。しかし、ことSES業界においては、スキルだけでは評価されるとは限りません。
では、本当に現場で求められるものは何なのか?
それは、「当事者意識」「主体的な行動」「コミュニケーション力」「調査力」 です。
技術が多少不足していたとしても、これらの能力がある人は現場で評価され、成長し続けることができます。
スキルを磨くだけでなく、現場適応能力を鍛えることこそが、SESエンジニアとして長く活躍するためのカギとなります。
スキルがあっても、それだけでは評価されない理由
エンジニアとしての技術力を身につけることは大切ですが、スキルがある=即戦力というわけではありません。
それはなぜか? SESの現場では、スキルよりも「いかに現場に適応できるか?」が評価の対象になるからです。
現場では以下のようなことが求められます。
- 「この環境において、どう動くのがベストか?」を考えられること
- プロジェクトの背景を理解し、適切な質問ができること
- 業務フローや社内ルールを早く把握し、それに沿った立ち回りができること
このような「対応力」「当事者意識」「調査力」が備わっていないと、いくら技術スキルが高くても現場では評価されません。
逆に、スキルが多少不足していても、「周りの動きを見ながら、どうすればプロジェクトに貢献できるかを考え、主体的に動ける人」**は、SES業界において非常に重宝されるのです。
「技術がある=現場で通用する」ではない理由
技術があることは重要ですが、SESの現場では、以下のような理由で「技術力があればOK」とはならないのが実情です。
技術スタックや開発ルールは現場ごとに異なる
あるプロジェクトでは「Reactが必須」とされていても、別のプロジェクトでは「Vue.jsのみ」となっていることがあります。また、コードの書き方や命名規則、開発プロセスのルールも、企業やチームによって異なります。
つまり、「この技術が使えるから大丈夫」ではなく、「この現場では何が求められているのか?」を早く把握する力が大切なのです。
✅ 良いエンジニアの動き方
「技術的にはAのやり方が最適だが、この現場ではBの方法が推奨されている。まずはBに従いつつ、改善できるポイントを探していこう。」
🚫 ダメなエンジニアの動き方
「Aの方が効率的なのに、なぜBを使うのか?とりあえず自分のやり方で進めよう。」
柔軟に適応する能力こそ、SESエンジニアに求められる力です。
「スキルがある人」よりも「話が通じる人」が求められる
SESの現場では、エンジニア同士だけでなく、プロジェクトマネージャーや顧客とのコミュニケーションが発生します。
そのため、どんなに技術スキルが高くても、「話が通じない」「質問が下手」「情報共有ができない」 エンジニアは評価されません。
例えば、以下のような状況を考えてみてください。
🚫 NGな例(悪い質問)
「この機能ってどう作ればいいですか?」
→ 何がわからないのか、何を試したのかが伝わらず、質問された側が困る。
✅ OKな例(良い質問)
「この機能の仕様について、〇〇の部分が曖昧なのですが、Aのように実装する認識で合っていますか?」
→ 事前に調査をして、明確なポイントを絞った質問なので、回答する側もスムーズに対応できる。
SESの現場では、「分からないから質問する」ではなく、「分かるために調べた上で、明確な質問をする」ことが重要です。
SESエンジニアが現場で評価されるポイント
では、実際にSESの現場で評価されるのはどんなエンジニアでしょうか?
✅ 評価されるエンジニアの特徴
- 当事者意識を持ち、自分の役割を理解して動ける
- 仕様が曖昧な部分を主体的に質問し、認識のズレを防げる
- わからないことがあれば、まず自分で調査した上で質問できる
- チーム内の動きを見ながら、適切な情報共有ができる
- 現場ごとのルールや文化に適応し、円滑に業務を進められる
こうした能力を持つ人は、スキルの有無に関係なく、どの現場でも「信頼できるエンジニア」として評価されます。
「スキルがなくても活躍できる人」の特徴
「スキルがないと現場で通用しない」と思われがちですが、実はスキルがなくても活躍できるエンジニアはいます。
それは、以下のような行動ができる人です。
✅ 「このプロジェクトの目的は何か?」を意識できる
→ 単に「言われたことをやる」ではなく、「なぜこの機能が必要なのか?」を理解しようとする。
✅ 「誰が何に困っているか?」を考えられる
→ プロジェクトメンバーの動きを見て、自分がサポートできることを探せる。
✅ 「わからないことをそのままにせず、調べる習慣がある」
→ 「この仕様が分からない」となったとき、まずは過去のドキュメントや社内のナレッジを探してみる。
こうした行動ができるエンジニアは、たとえ技術的なスキルが不足していても、現場で信頼される存在になります。
まとめ
スキルだけではなく、現場適応能力を鍛えよう
SES業界では、技術力よりも「現場での立ち振る舞い」「当事者意識」「調査力」が評価されます。
✅ スキルがあっても、現場ごとのルールや技術スタックに適応できなければ評価されない。
✅ 主体的に質問し、プロジェクト全体の目的を理解することが大事。
✅ 技術がなくても、当事者意識を持って行動できる人は活躍できる。
SESで長く活躍するためには、技術を磨くだけではなく、現場適応力を鍛えることが重要です。
「このプロジェクトで求められているのは何か?」を意識し、積極的に行動していきましょう!